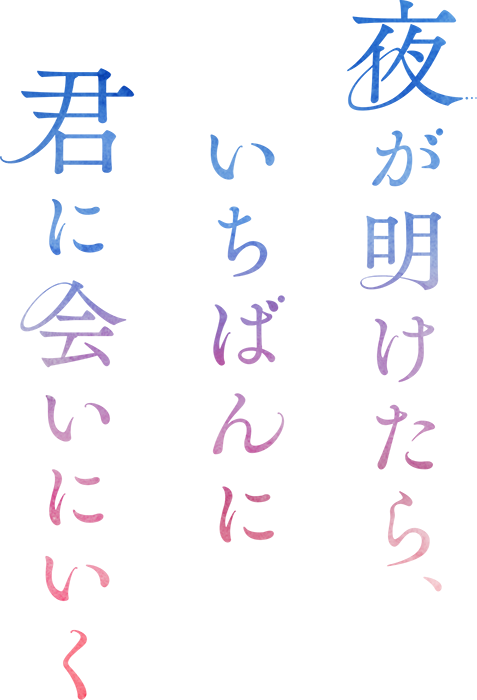Production Note
取材・文:遠藤薫



「この小説は酒井さんに合うと思うので、読んでみませんか?」別作品の準備中に酒井麻衣監督がプロデューサーから手渡された本こそ、汐見夏衛の「夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく」だった。「茜というキャラクターは自分が傷つきたくないから、がんばって優等生を演じているのに、結果人の顔色をうかがって言いたいことを我慢している女の子。そんな子が青磁という男の子に出会って、少しずつ心を解放していく姿に惹かれました。学校の屋上のシーンが特に印象的で、読んでいても爽快さを感じましたね」そう原作の魅力を語る酒井監督。だが監督の心に最も刺さったのは、コロナ禍以前に書かれた小説だったにも関わらず、“マスクが手放せない”というマスク依存とも思える茜のキャラクター設定だった。「今、この作品を映像化することで、もしかするとすごく救われる(中高生の)方々がいらっしゃるんじゃないかという気持ちですね。一番気を付けたのは、マスクをすることを否定しないこと。マスクを外すことを促すようなシーンを入れないことは、繊細に考えていきました。本心をさらけ出せない茜にとってマスクはお守りのようなアイテムですが、実際コロナ禍になって、同級生の顔を知らないまま学生生活を終えていく子たちもたくさんいます。だからいきなり、“マスク着用が個人の判断に委ねられる”と言われても戸惑うのは当たり前だし、心の整理をする時間が必要なんじゃないかなと。そんな方たちにこの映画が届いたらいいなという想いで、脚本を作っていきました」
脚本は、韓国出身の新進気鋭の脚本家=イ・ナウォンと監督の共同執筆。イが最初に全体の構成を作り、監督と丁寧に会話しながら細部を構築していった。「物語自体は茜の視点で描かれていきますが、青磁の気持ちも大切にしましょうという話はさせてもらいました。人間は誰でもそうだと思いますが、この2人も強くもあり弱い子たち。“人”をじっくりと描いていこうという気持ちが、ナウォンさんと早い段階で共有できたのは大きかったです」本作には、ボーイ・ミーツ・ガール的なキラキラした要素もあるが、同時に絶妙にリアルな「恋愛」の手触りもしかと内包されている。「キラキラ感を大事にしつつ、これは“2人の恋の物語である”という本質を常に忘れないようにとは意識していました。少女漫画だと恋のライバルが登場したりする展開もあり得ますが、この作品は一貫して2人が自分と相手と向き合うことに集中している……ある意味でちょっと珍しい物語。人が恋をする瞬間をとても繊細に描いたお話でもあるので、その瞬間をとことん突き詰めようと」誰もが一度は経験したことがあるであろう“恋をする瞬間”。その儚くもきらめく瞬間を切り取った本作は、ファンタジックな美しさとハッとするほどのリアリティを兼ね備えている。
W主演を務めるのは、白岩瑠姫(JO1)と久間田琳加というフレッシュな2人。JO1のメンバーとして、今や絶大な人気を誇る白岩だが、本作が映画初出演にして初主演作となる。白岩演じる類まれな絵の才能に恵まれる青磁は、透き通るような銀髪が特徴的で、その立ち居振る舞いも芸術家らしく自由奔放。決して人と群れるタイプではないのに、クラスメイトからは不思議と一目置かれる存在だ。久間田演じる茜は、学校では常にマスクを着用し、「優等生」を演じながら本心を隠してクラスや周囲に溶け込もうとする少女。同級生たちをまとめようと奮闘する責任感の強さからも、本来の生真面目さがうかがえる。 「正直2人とも、とても難しい役だったと思います」と監督。特に本格的な芝居経験がなかった白岩は、当初かなり緊張していた様子だったとか。だが多忙なスケジュールの合間を縫って、撮影前から熱心にリハーサルを重ねる姿はストイックそのもの。撮影が始まってからも貴重な撮休の日を使って、「役をつかみたい一心で」監督と共にリハーサルに臨むうち、その芝居の精度は目に見えて上がっていった。
一方の久間田は、白岩とはまた別のアプローチで、クランクイン前から熱心に役作りに励んでいた。それは茜が、学校では「マスクを手放せない」キャラクターであり、マスクというアイテム自体がこのご時世センシティブなテーマをはらんでいるからでもある。汐見夏衛による同名原作自体はコロナ禍前に書かれたものであるし、映画でも劇中コロナを匂わせる表現は皆無。だが監督は本作を通じて、「マスクをし続ける=悪いこと」とは絶対に表現したくなかったと語る。久間田もその感覚を共有すべく、クランクイン前から現役の高校生にマスク事情を直接ヒアリングするなど、熱心に役作りに励み、茜の抱える心の秘密と向き合い続けていた。
青磁と茜を演じる上で、それぞれに絶え間ない努力を続ける白岩と久間田に対して、監督はこう述懐する。「どちらかが芝居で引っ張るというより、2人が互いに120%でぶつかり合った時に、何が生まれるのか?というのを待っていた感じです。2人とも実際のキャラクターは役とはかなり違うんですが、役になった瞬間に絆が生まれるんです」
実は白岩も久間田もかなりの人見知りタイプ。撮影序盤はセリフ以外で言葉を交わすことがほとんどなく、見かねた監督が白岩に「今後アドリブ芝居も出てくるだろうから、ちょっと話かけてみて下さい」とアドバイス。白岩は久間田が役に集中している時間を妨げてはいけないのではないか?という配慮から、あえて話しかけるのを躊躇していたそうだが、監督のアドバイスには素直に従う。翌日「今日は自分から挨拶しましたよ!」と報告する無邪気な姿に、監督も思わず笑顔になるのだった。
撮影は2023年の1月から2月にかけて、実質2週間強というタイトなスケジュールで行われた。青磁と茜が2人の時間を過ごす学校の屋上は、関東近郊の専門学校をお借りしてのロケ。屋上で大事なシーンが多く撮られるため、ロケーションは屋上最優先で探し、青磁がいつも1人で絵を描いているアトリエは「秘密基地のようにしたい」という監督のリクエスト通り、秘密めいたワクワクするような空間を美術部が細部まで作り込んでいく。原作のイメージに忠実に「柵がない屋上」も監督の強いこだわりで実現した。(*実際は安全のため生徒は立ち入り禁止。もちろん撮影は安全第一で行われた)
真っ青な冬の空の下、キラキラ輝く銀髪をなびかせながら、慣れた手つきでキャンバスを組み立て、絵の具を器用に混ぜ合わせていく青磁。一連の所作も美しいが、絵画経験のなかった白岩は道具一式を自宅に持ち帰り猛特訓。絵画監修として現場にも度々訪れたアーティスト・朝霧レオのもと、撮影前からみっちり絵画講座を受け、万全の状態で撮影に挑んでいた。「白岩さんにはたくさん練習してもらいましたが、今回は作法やテクニックというよりは絵を描くというロマンを大事にしました。青磁が絵を描いていく工程も面白いですし、絵の具を混ぜ合わせる瞬間なども見ていて魅力的だなと思うので、そういう青磁を見て茜も何か感じるところがあるだろうなと。その感覚を映像として体感できるように撮影していきました。この作品は“色”のお話なので、色を作り上げる楽しさを白岩さんにも大切に演じてもらいたかったんです」
一方の久間田も、決して誰にも吐露することのできない悩みを抱えながら、青磁との出会いにより、にわかに心の内側が色づき、次第に青磁に心惹かれていく様を繊細に表現することに腐心。映画撮影後に解禁となったティザービジュアルのコピーは、「無彩色で息苦しいこの世界。救い出してくれたのは君でした――」というもの。このコピーはまさに茜の心情を表したもの。茜が生きる鈍色の世界に鮮やかな「色」を与える青磁により、茜は目の前の世界の美しさに気付いていく。久間田はマスクをつけての演技が多い本作において、そんな心のきらめきや感情の起伏を目の動きを活かした演技や些細な所作、声色の変化により巧みに演じ上げていた。白岩と久間田ともに撮影中に印象的だったのは、撮影中の監督からの細かな指示に対し、両社とも「了解です!」と迷わず答える柔軟さ。そんな白岩と久間田に対し、監督は感慨深げにこう語る。「白岩さんも久間田さんもこちらが言ったことに対しての反応が速いし、純度の高いお2人だなと思いました。考え方が凝り固まっていないので、吸収する力がとても強いお2人でしたね。」
どのシーンにおいても、リテイクのジャッジが速い酒井監督。そこには監督ならではの、「グッとくるか、こないか」という明確な判断基準があった。例えば屋上にはしご伝いに青磁が茜を引き上げるシーンも、「もう少し力強さがほしいな」とスタッフと盛り上がる監督。スタッフがお手本を実演する様子を、真剣な目で見つめる白岩。その後、明らかに芝居が変わった白岩にすぐに「OK!」を出す監督には迷いがない。「グッとくるからOKと言いたいんですが、俳優さんに“今のはグッとこないんです”と言うのは演出としては違うと思っていて。どうやったら私自身が彼らの着火装置になれるかということだと思います。白岩さんも、久間田さんも脚本をすごく読み込まれているのは分かっているし、セリフもきちんと入っている。でも気持ちで思っていることをお芝居として外に出すことって、テクニック的なことも必要になってくるし、どうしても(気持ちと芝居に)差異が生じることもあるんです」そんな時監督は直接2人の元へ足を運び、「今何考えてる?」「ときめく時って、体ってどうなる?」など、あえてシンプルな言葉で問いかける。「私はきっかけを与えさせてもらうだけなんです。でもそれで気持ちを再確認した後のお芝居って、ちょっと違ったりする。自分がときめいた瞬間を探して……例えば呼吸が深くなるとか、そういうことに気付くきっかけになればいいなと。演出は料理と同じだと思っていて、新鮮なまま食べた方がおいしいものもあれば、じっくり煮込んだ方がおいしいものもある。天候やその日の気分によって、スパイスを入れた方がいい時もありますよね。撮影も同じようにいろいろなタイプがあって日々変動していくのなので、必ずしも事前に思い描いていたものが正解とは限りません。現場で感じたことをもとに、皆で作っていくことを心がけています」
32歳の若き監督を支えるスタッフ陣は、現場でも抜群のチームワークを見せる。『劇場版 美しい彼~eternal~』に参加したスタッフも多数いたという今回の酒井組について、「本当に相性のいいチームです」と監督。「個人的には年齢は関係ないというスタンスでやらせてもらってはいますが、相性や好みは誰にでもあると思います。その点この組は、“こういうものを作りたい”と目指している先が同じ方々ばかりだったので、私が助けてもらうことの方が圧倒的に多かったです」監督が現場で次々に思いつくアイディアを全員で面白がり、スタッフ側からも遠慮なくアイディアを出していく。年齢差やキャリアが障壁となることはなく、各自が自由に意見を言い合える空気感に満ちていた現場は、酒井組の大きな特徴でもあった。チームワークの良さは、絶妙なスケジューリングにも顕著。真冬の撮影は日が落ちるのが早く、常に時間との戦いを余儀なくされるものだが、全員が一丸となってギリギリまで粘りながら日々の撮影を乗り切った。「夕方4時くらいから暗くなってしまうので、そこは本当に大変でした。日によっては撮りこぼすこともありましたが、演出部さんがうまく調整してくれて。天候の読みもばっちりで、雪や雨の日はきちんと撮休にしてくれたのもありがたかったです」この時期だからこそ撮れた、美しく澄んだ空の画も冬の撮影の賜物だ。
また【色の映画】だからこそ監督がこだわったのが、廃遊園地から見る茜色の夕景。青磁がどうしても茜に見せたかったこの夕焼けは、リアルタイムの日没前を狙って撮影にトライ。心地いい緊張感の中見事に美しい夕焼けがカメラに収められたことは、撮影隊の士気を上げるに十分だった。
青磁と茜のクラスメイトたちにも、今後が楽しみな若手俳優たちが多く出演。今回その全員に、キャラクター付きのプロフィールが用意されていたという。何の部活に入っているか、誰と仲がいいかなど、1人1人のバックグラウンドを明確に理解したうえで役を演じている俳優たちゆえ、「自然とクラスに一体感が生まれました」(監督)というのも納得だ。
また、茜の母・恵子を演じた鶴田真由、継父・隆を演じた吉田ウーロン太、青磁と茜の担任教師を演じた今井隆文、そして青磁の知られざる背景を知る美術教師・岡崎を演じた上杉柊平という、練達の共演陣も共に印象深い好演を見せる。「若いキャストが多い現場に、お芝居の面でもとてもいい影響を与えてくれました」
監督のこだわりは、キャラクターのルック…衣裳やヘアメイクにも及ぶ。「今回特にこだわったのは制服です。多様化の時代に合わせたいという願望も含め、選択性で自由のきく制服にしたいというのは最初から決めていました。青磁に至ってはいつもツナギで、制服ですらありません(笑)。それは青磁の自由奔放さを表現するためでもありますが、いつ絵の具で汚れてもいいようにという理由付けにもなっています」
本作を色に例えると「透明」と即答した監督。「純度がとても高い恋の物語なので、透明感がある映画にしたいなと思いました。繊細なガラスの向こう側にあるような、透き通った世界のイメージです」監督の作品はその映像美が話題になることも多いが、意外なことに美しさにはそこまでこだわりはないとも語る。「せっかく映像として世に残るものなので、自分がときめけるもの、ワクワクするものにしたいという想いが強いです。あとは映画を見た方の生活がちょっと楽しくなるような、日常や人生の彩りになれたらいいなとはずっと思っています。“ほら、お前の世界も綺麗だろ”という青磁のセリフが好きなんですが、そういうことを見た方が感じてくれたら嬉しい。見ようによっては、自分の世界も意外と綺麗かもしれないと。映画館で綺麗な夢を一緒に見ましょう!」




Interview
久間田琳加さん 特別インタビュー
取材・TEXT:映画評論家・松崎健夫
Q:本作の観客が “茜” のキャラクターに共感し、“茜” ファンが増えているという現象に対して、久間田さんはどのように受け止めておられますか?
わたしも原作を読ませていただいた時から、茜は「ものすごく共感ができるキャラクターだな」と感じていたので、演じる時もそれがより多くの方に伝わったらいいなと思いながら役作りをしていました。いろんな感想を見て、少しでもそこが伝わったのかなと思えた時に、初めてほっとできました。自分が伝えたいところは伝わったなと思って、とても良かったです。
Q:原作を読まれた時、茜はどんなキャラクターなのだと捉えましたか?
茜自身は言いたいことをはっきり言えないというキャラクターで、わたしも「自分にもそういうところがあったなぁ」と学生時代の頃を思い出しました。学校という社会の中では、周りに合わせてしまったりしていましたね。とにかく茜は、目の前にあることを頑張るのに精一杯で、常にパンクしちゃいそうな状態。キャパが超えそうなところをギリギリ歩いているような感じで、だけど全部をしっかりやりたいという性格。でも、青磁の絵を見て感動したり、人を思う気持ちがあったり、感受性の豊かな子なのだと思いました。
Q:この映画は、茜や久間田さんと同年代の観客だけでなく、親にあたる世代の共感も得ています。それは、いつの時代も、若者は“言いたいことをはっきり言えなかった”という普遍性があるからではないかと感じました。一方で、SNSでは匿名性を盾に“言いたいことを言う”というような反動が生まれているようにも感じます。
そうですね。やっぱり顔を出したり、名前を出さずに言いたいことを言える環境が、わたしたちにとってはあまりにも身近になり過ぎて、全ての基準がSNSになってしまっている。SNSというのは、“はっきりと言いたいことを言う”本当の自分ではあると思うのですが、それを表に出しづらくなったというか。茜が青磁に言われてしまうように、顔色を伺って生活してしまうところは、SNSがあるからこそより強くなってしまったという世代なのかも知れないですね。
Q:原作はコロナ禍以前に書かれていたものですが、奇しくもコロナ禍を経たことで、観客は茜がマスクを外せないことと現実のコロナ禍での状況とを、地続きのものとして勝手に推し量っているという不可思議がありますよね。
茜の場合は、マスクをすることで何を思っているのかを判らないようにしているのだと思うんですけど、その感覚ってわたしも演じながら感じたことなんです。確かに、すごく楽だなって感じたんですね。マスクを着けている時の方が、生活しやすいなって感じてしまって。本当は、ちゃんと気持ちを伝えた方が、何を言いたいのかがはっきり判るはずなんです。だけど、遠回しに伝えたりして。どう伝えたとしても「本音を言い過ぎたかな?」と思ったりするので、その防衛策みたいなものが、マスクに繋がっているような気がします。
Q:今回、マスクを着けて演技をされているので、顔の半分が隠れてしまいますよね。そうすると、表情が表現しにくいという難しさがあったのではないですか?
最初はめちゃくちゃ不安でした。たまたま、<外国人は口元を見て判断する>という記事をSNSで目にしたばかりだったので、口元が見えないことは表現するにあたって難しいというか、わたしにとっては挑戦でした。監督にもその不安を伝えていたのですが、だからこそオーバーに演じるというのではなく、内から感じたことを思えば、それが自然と出てくるのではないかという結論に至ったのですが、撮影に入ってからは、いったんその不安は置いておこうということになりました(笑)。
Q:久間田さんの演技が素晴らしいと思ったのは、茜の台詞を放っている時ではなく、周囲の役者が台詞を放っている時のリアクション(表情)によって、観客が茜の裏腹な心情を悟るという点にあります。
自然発生のことだったと思います。そこを意識してやったわけではなくて、環境を見て自然に起きていたことなのかも知れないです。例えば、誰かと対話をしている時に、わたしは自分のことをぜんぜん喋れないんです。友だちと一緒にいる時も、ぜんぜん話せなくて聞く側に回りがち。そういう“聞く”ということが癖づいているところや、いったん人の話を聞くということが、自然に茜とリンクしたのかも知れません。それでいうと、わたしもすごく周りを見過ぎるタイプで、茜と近いものを感じます。
Q:これは酒井麻衣監督の演出によるものだと思うのですが、マスクで表情が見えにくいからなのか、指先や足元などのクロースアップを多用することによって、“感情”の表現を試みているのも特徴だと感じました。例えば、教室でアンケートの文章を読み上げる時に、指先の動きで“とまどい”が表現されていましたよね?
はっきりとは言われていなかったと思うのですが、監督はシーンの説明をする時に、ご自身で動いてみせてくださることがあったのです。監督自身が茜になっているというか(笑)、時には青磁になりきっている時もあって。ふたりに憑依している瞬間があった。その動きから、茜のキャラクター像に対するインスピレーションを受けたことはあったと思います。
Q:それから、冒頭の団欒場面も素晴らしいと思いました。それは、鶴田真由さん演じる母親と吉田ウーロン太さんが演じる継父に対する茜の声のトーンが微妙に異なることで、何ひとつ台詞で説明することなく、一発目の会話だけで観客は彼女の複雑な家族関係を推し量ることになっているからです。
鶴田さんに話しかける時は声が少し高くて、吉田さんに話しかられた時は、構えている分、ちょっと低い。本気で思っていない時のような声だったと、いま言われて気付きました。



Q:原作は茜の一人称で心情が綴られていますが、映画の方では茜の心情がモノローグでは説明されていないという違いがありますよね?
思い返せば、映画やドラマでは、“モノローグ録り”というものがあって。それはそれで、大変な思いをすることがあるのですが、今回モノローグがなくても茜の心情が伝わったのであればよかったです。作品の中の話とはいえ、クラスメイトが自分の言葉を聞いてくれない状況だったり、自分の爪を傷つけるようなシーンがあって、わたしの中でも撮影期間中に日々を生きることがしんどいと感じた時がありました。だから、よりそのまま、全部の気持ちが茜として出ていたのであれば、よかったなと思います。
Q:実際の日常生活でもよくあることですが、撮影期間に久間田さんが茜として生きていた結果、相手の気持ちを何となく察するという行為が、自ずと実践されて映像に刻まれていたのかも知れませんね。
毎日撮影に向かうという日々でしたが、茜の気持ちになって「また、この1日がはじまる」「みんなが話を聞いてくれない」「青磁ともうまくいかない」と思うと、とにかく体が重いというか。いかに「この現状をどうするのか?」と考えることがありました。
Q:酒井麻衣監督からは茜を演じるにあたって、どんなアドバイスがあったのでしょうか?
「わたし、こんなに頑張っているのに、誰も聞いてくれない!」という悲劇のヒロインのような感じには絶対したくない、と打ち合わせでお話しさせていただきました。ただ、ただ、目の前にあることを頑張っているだけなのに、次から次に問題が積み重なってしまっている。だから応援したくなるような役柄にしたいということが、大元としてあったと思います。シーンの撮影前には監督から説明があって。お互いの信頼関係を基に「茜はここまでの道のりで、こういうことがあったよね」といった確認があったのは心強かったです。だから、現場ではひとつひとつを丁寧に追っている感じがしていました。
Q:茜と同世代の高校生の方に“マスク事情”をヒアリングして、役作りの参考にされたともお聞きしました。
わたしが高校生だった時代にはマスクが身近ではなかったのですが、コロナ禍を経験している今の子たちにとっては、違う意味でも身近になっていますよね。それで気になって、お話を聞いたら「マスクをしている方が楽です」という言葉が第一声だった。「顔を見られるのが恥ずかしい」と話していたんです。入学式からマスクを着けているので、外すタイミングがわからなくなって、ハードルが上がっている。だから、お弁当を食べる時も1回マスクの片耳を外して、食べて、また片耳に着ける、ということを繰り返すそうなんです。そいうところを、実際に茜がお弁当を食べるシーンに活かしました。いまの高校生と茜とでは、マスクを着ける理由が違うとはいえ、ものすごく身近なものになっているということを感じましたね。
Q:劇中におけるマスク姿の茜と素顔の茜、演じる上でのルール分けはあったのでしょうか?
マスクを着けないシーンは、茜が家にいるときと青磁くんと打ち解けたあとですよね。台詞にあったわけではないのですが、空気を吸うようにしていました。マスクを着けていると口元が押さえられている分、こもっていてしんどい。その反動で、マスクを外した時に空気を吸うというのが凄く気持ちよくて。撮影が冬だったので、空気も澄んでいて、より綺麗だった。そういったことは意識していました。
Q:茜役を演じる上で、クランクイン前に参考にした作品(映画・ドラマ・文学・漫画 問わず)やキャラクターなどはあったのでしょうか?
原作ですね、いつも原作を握りしめていました(笑)。本で読んでいましたし、いつでも確認できるように電子書籍も買っておいて。先ほどの質問にもあったように、原作には(台本のト書きにはない)茜の気持ちがはっきりと書かれているから、そこにかなりのヒントが詰まっている。こういう時に茜はどう感じるのか?ということを、原作に戻って確認して、めちゃめちゃ読み込みました。台本は、フリーで演技ができるようなシーンも多くて、例えば、<楽しそうな青磁と茜>と書いてあったら、それを自分で埋めていく必要もありました。だから台本には、その時青磁に対してどう思ったのかを書き込んでいました。屋上でペンキを塗り合うシーンには、台詞がひとつも書かれていなくて。そこで芝居を埋めていくのは、わたしと白岩(瑠姫)さんの役割なのです。白岩さんとは、撮影の途中からそういったことをお互い話すようになりましたね。



Q:この映画では、高校生や若い男女を主人公に据えた多くの恋愛映画とは異なり、手を繋いだり、キスをしたり、直接的なふれあいがなくとも、青磁と茜が互いに惹かれていく様が巧みに描かれていますよね?
演じていて思ったのは、「こういうところに青春って詰まっていたんだよな」ということ。ただただ、じゃれ合って、遊んでいる瞬間や、直接的なふれあいがなかったとしても、キラキラしたものって身近に転がっていたんだということを思い返させてもらった感じがします。そんな気持ちが、いつのまにか消えてしまっていたことを思い出させてくれる。「こういう形もあるよ」と提示してくれて、「お互いを思い合う究極形態はこれだよ」という感じもある。より、今の時代にぴったりな気がしました。
Q:青磁の描いた絵に対して茜が惹かれた理由を、久間田さんはどう考えていますか?
やっぱり、ぜんぜん自分にはない要素を持っているからこそ、魅力的に感じたというか。自由に感じたまま絵を描いている姿に「すごいな!」と感じて、その場の空気を持っていかれてしまう。そこを、茜は魅力的だと感じたのだと思います。
Q:茜の部屋の装飾がとても印象で、作り込みが細かく、そのことが彼女のキャラクターを表現しているようにも感じました。
わたしも全く同じことを思いました。撮影の初日が、おしゃれな小道具でぎゅうぎゅうに詰められた茜の部屋だったのですが、屋根裏部屋の斜めになった天井が、より不安定な気持ちにさせるように私は感じ取ったんです。ぐらついた感じを受け取ったというか。その場でお聞きしたら、小物は全部アンティークで、ショップへ買い付けに行ったものだと仰っていて。とても凝っているなと思いました。
Q:酒井組がこれまでに久間田さんが参加された作品と違っていたところや、監督の演出、画作りで印象に残っているところがあれば教えてください。
まず、「物凄く自信を持たせてくれる」ということがあると思います。わたしが不安に思っていても「大丈夫だよ、あなたは素敵なのだから」という声かけを、大事にしてくださるんです。「いまのままで魅力的だよ」ということを、言葉にしてちゃんと伝えてくださる。それは、撮影期間中ずっと前を向くことができた理由のひとつです。酒井監督は引っ張って行ってくれる存在。話しかけやすい環境にしてくださっていたというか、お互いに対等な関係なのだと感じさせてくださった。「この人になら、この姿を見せられる」という感覚で、フラットで居やすかったです。それは年齢によるものなのか、人柄なのか。いろんな要素が集まっていたからなのだと思うのですが、だからこそ安心して芝居に集中できたと感じていました。
Q:SNSなどでは、「恋愛映画の域を超える感動」「令和の新しい青春映画の傑作」「茜が他人とは思えない。自分も茜のようにこの映画に救われた」、などの感想があふれていて、多くの映画ファンを魅了しています。久間田さんは、どういった要素に、観客が「刺さった」と思いますか?
わたし、公開されてから映画館へ2回観に行ったのですが、それで初めて作品を客観視できたんです。否定されているような気持ちに一切ならないというか。わたしの解釈や伝えかた次第では「マスクを取って幸せだよ!」みたいな、無責任な感じに受け取れる場合もあると思うのです。そんな感覚を強要する感じがひとつもない。でも、茜は茜で、作品の中ではちゃんとゴールに向かっていますよね。その人としての“在り方”を否定はしないけれど、凄く寄り添ってくれているのだと映画を観ながら思いました。
Q:久間田さんがおっしゃるように、この映画からは“救い”のようなものを感じます。現代社会は厳しい環境にありますが、「言いたいことが言えない」「生きづらさや息苦しさ」を感じている方々に、この映画を通してどんなことを伝えたいですか?
“救いになった”というコメントは、わたしのところにも届いていて。最後に向けて明るい気持ちで終われるというか。そっと背中を押してくれるようなラストだなと、わたしは思っていて。この映画で描かれていることは、必ずしもそれぞれが抱えている悩みと合致するわけではないと思うのですが、自分を大切にすることを教えてくれる作品になっているのだと考えています。
Q:最後に、既に映画をご覧いただいた観客の皆さま、そして、これから映画を観る観客の皆さまにメッセージをお願いします。
わたしは『夜きみ』を3回観たことになるのですが、茜の学校生活の話、茜の家族の話、茜の対人関係や青磁との物語など、いろんな角度から感じ取れる感情があるのだと思っていいます。何か答えを求めたくない時や、何か答えが欲しいわけじゃない時。それを言葉にすることが難しいということを映画にした作品で、いろんなところにヒントが散りばめられている。何か弱った時に、みなさんの背中を押してくれるような作品になっているのではないかと演じながら思いました。みなさんにとって、何かのきっかけとなる作品になったらいいなと思います。